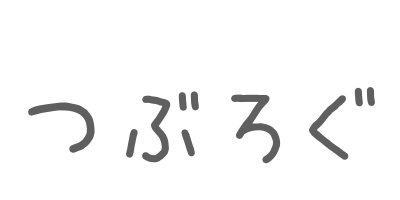阿波踊りといえば、徳島県で400年以上の歴史を持つお祭り。
その伝統的なお祭りが、東京都でも開催されています。
それが、杉並区高円寺(こうえんじ)で毎年8月に行われる「東京高円寺阿波おどり」。
昭和32年の町おこしがきっかけで始まりました。
私も毎年夏になると、家族で高円寺阿波おどりを見に行きます!
毎年100万人前後の見物客が訪れて、熱気ムンムンのお祭りです。
「踊る阿呆に見る阿呆。同じ阿呆なら踊らにゃそんそん♪」
高円寺阿波おどりの由来や見どころ、屋台に穴場など、お得な情報などたっぷりとご紹介しますね。
ぜひ、参考にしてみてください。
高円寺阿波踊りの由来や人数・来場者数など
東京高円寺阿波おどりの由来は、昭和32年8月。
現在の、パル商店街振興組合の青年部が誕生した「記念行事」として考えられたのが発端です。
隣の阿佐ヶ谷ではすでに「七夕祭り」が始まっており「負けてはいられない!」と奮起して始めることになったとか。
神輿は高価で手が出ないし、商店街は狭いので盆踊りはできない…。
そんな試行錯誤を繰り返し、たどり着いたのが徳島の阿波おどりでした。
当時は、本場の徳島に遠慮して、白塗り化粧をほどこした「高円寺ばか踊り」に決まったそうです。
第1回目の観客は2,000人でした。
高円寺阿波踊りには外国人も参加
本場の徳島の阿波おどりの師匠からも指導を受け、さらにパワーアップ。
昭和38年には正式に「高円寺阿波おどり」と名前を変更しました!
それ以来、各国各地へ遠征・出演をして踊りを披露しています。
現在では、約60名の外国の方も参加しているそうです。
近隣の小学生もボランティアスタッフに
東京高円寺阿波おどりには「踊り手の笑顔を通じて街や人が元気になってほしい」という想いが込められています。
近年では、近隣の小学校の生徒たちが阿波おどりを支えるボランティアスタッフとして関わるなど、地元の人たちや商店街とも深く密着し、幅広く充実したお祭りとなっているんですよ。
平成31年(2019年)には出演者約1万人、観客動員数が101万人にもなり、毎年熱い暑い夏の風物詩となっています。
毎年、総距離3.2キロメートルを3時間×2日間ぶっ通しで練り歩きます。
過酷なお祭りですが、見ている方にとっては本当に圧巻です!
高円寺阿波踊りの特長や見どころは?
高円寺阿波おどりは「流しおどり」と言って、隊列を組んで、前に向かって踊りながら進むスタイルです。
踊りの基本は3種類。
- 女踊り…「腰を落とす」「手と足を同じに出す」「つま先から地面に付ける」で優雅でしなやか
- 男踊り…力強くダイナミックで時にひょうきん
- 子供踊り…小学生以下
太鼓・鉦(カネ)・笛・三味線などの鳴り物の迫力ある大きな音は存在感があり、かっこいいの一言に尽きます。
踊りのグループ「連」は100以上!徳島の連や海外からも!
踊りのグループ「連」が、それぞれオリジナルの衣装を着て、それぞれの踊りを披露します。
「女踊り」がメインの連や鳴り物が独特な連など、どれ1つ同じ連がないので見ていて飽きません。
参加連は地元だけでなく、徳島県や各地方、また台湾などの海外からの参加連も増えているそうです。
2019年は、出演者約1万人、112連が参加しました。
高円寺阿波おどり連は全部で30連です。
(1981年に「高円寺阿波おどり連協会」が発足し、17連からスタートしました)
各連、感染症対策に細心の注意を払いながら撮影、制作した動画を公開。まだまだ活動することが難しい状況にありますが、現状に向き合いながら少しずつ動き出そうとしています。各連の動画はこちらから↓https://t.co/9g5mDkUnxi#東京高円寺阿波おどり #高円寺 #阿波おどり pic.twitter.com/inGdfJFTBG
— 東京高円寺阿波おどり (@awaodori_koenji) March 25, 2021
有名連だけでなくどれもおすすめ!
有名連(人気連)と呼ばれるものには、飛鳥連、天狗連、舞蝶連などがあります。
しかし、それぞれの連によってパフォーマンスが違います。
「これが見どころ!」と、1つ述べるのは非常に難しいです。
初めて見る人たちにとっては、どれも楽しいものです。
土日が本番ですが、実は前日の夕方、金曜日からプレ踊りがあります。
全部の連が参加するわけではないのですが、徐々にテンションが上がってきます。
劇場での観覧もできます(秋にもあり)
土日当日には、午前中、駅の近くの座・高円寺という劇場でも、座ってゆっくりと観覧することができます。
(自由席 チケット1,000円)
こちらは、「流し踊り」ではなく、ステージ上での「組み踊り(盆踊りのようなもの)」をベースにしています。
また、夏だけでなく秋にもこの組み踊りは行われます。
夏に見逃した方も、また見たい方も、ぜひチェックしてみてくださいね。
終演後には体験教室も行われるそうなので、体験してみませんか?
高円寺阿波踊りのルート・運行表(穴場や桟敷席はある?)
高円寺阿波おどりは8つの演舞場が設けられています。
↓ 参考に、2019年のルート(運行表)です。
20時までふれおどり開催中です。明日・明後日は第63回、東京高円寺阿波おどり!17〜20時開催。お目当ての連は運行表でお探しください。 #koenji #awaodori 公式サイトはこちら→ https://t.co/0SHCNRdRUC pic.twitter.com/R5RIsGKPJo
— 高円寺ルック商店街 (@koenjilook) August 23, 2019
- 中央演舞場
- ひがし演舞場
- 純情演舞場
- パル演舞場
- 桃園演舞場
- みなみ演舞場
- ルック第一演舞場
- ルック第二演舞場
JR高円寺駅から東京メトロ・丸ノ内線新高円寺駅までの大通りは、大変混雑します。
私は毎年、子供たちの友だちやママ友が入っている連がスタートするところに待機して観覧しています。
残念ながら、場所取りはできません。
なるべく人の少ないところで上手に鑑賞するしかないのですが、比較的前の方で見られる穴場スポットをこっそり教えましょう!
穴場はルック第一・第二演舞場
ルック第一・第二演舞場は、スタート地点。
道幅が狭い通りではあるのですが、踊りを近くで見ることができます。
運が良いと、真ん前で見ることができますよ。
踊り手さんがすぐそばで見られるので、迫力があり、一体感が味わえて本当にテンションが上がります。
子供達も、友だちの踊っている姿を間近で見て「かっこいい〜」と惚れ直したりしていました。
また、ちょこちょこと移動しながら見るのもオススメです。
(あまり遠くに行きすぎて迷子にならないようにしてくださいね)
高円寺阿波踊りの桟敷席は?
また、協賛金のお礼として、演舞場特別桟敷席が設けられています。
1口当たり①8,000円 ②7,000円 ③6,000円で最大5口まで申し込むことができます。
7月にハガキやインターネットで申し込むことができます。
協賛金は、お祭りが中止になっても払い戻しはありませんのでご注意を。
高円寺阿波踊りの時期はいつ?(開催日程や行き方など)
「高円寺阿波おどり」は毎年8月下旬の土曜日・日曜日の2日間に渡り開催されます。
(ちなみに、2019年に行われた第63回東京高円寺阿波おどりは、8月24日(土)・25日(日)に開催。)
時間は午後5時から夜8時までで、嵐のような悪天候でなければたいていは開催されます。
高円寺阿波踊りの場所や行き方
- JR「高円寺駅」(新宿駅から6分)
- または東京・メトロ丸ノ内線「新高円寺駅」駅(新宿駅から9分)
駅周辺の商店街や、高南通りの8演舞場です(高円寺阿波踊り公式サイトの運行表はこちら)。
ただし土日休日は、JR中央線快速は高円寺駅には止まりません。
JR総武線に乗ってくださいね。
駐車場は?交通規制があるので電車がベスト!
当日は、高円寺南、北(青梅街道・環状七号線・早稲田通り)は、午後4時10分から午後8時30分まで交通規制が実施されます。
車両の進入・通行はできません。
それ以外の区域にコインパーキングなどはありますが、当日は満車になる可能性も。
電車でのアクセスをお勧めします。
その日は既に、午前中からお祭りの準備で町全体がお祭りモードになっています。
早めに行って、高円寺を探検してみるのもいいでしょう。
私は地元に住んでいるので、ウロウロしたり歩いて帰れるのですが、当日は本当に混雑します。
終わった後は終電ギリギリという時間ではないので、余韻にひたりながら1駅歩いてみるのもいいですね。
高円寺阿波踊りでは屋台(露店)はあるの?トイレは?
お祭りの楽しみの1つに、屋台で買った飲み物や焼きそばを食べることがありますよね!
高円寺阿波おどりの場合はどうかというと、屋台村が出現します。
高円寺北口広場ブースと南口の中央公園ブースには、来場者の胃袋を満たしてくれるたくさんの屋台が出店されますよ。
時間は午前中やお昼から始まりますが、毎年異なるようなので、その都度確認してくださいね。
また、ブースではなくても所々に屋台があります。
食べたり飲んだりするには困りません。
ちなみに、高円寺駅南口広場では密かに公式グッズが販売されているようなので、ぜひチェックしてみてください。
レストランや飲み屋が出す屋台なので、普通の屋台にはないスペイン料理やタイ料理などに出会うこともありますよ!
最終日の終了間際の時間には、かき氷を子どもたちに無料でサービスしてくれる屋台もありました。
始まる前に腹ごしらえを
踊りが始まると、人混みの中を出たり入ったりするのが難しくなります、
始まる前に、少し食べておくことをお勧めします。
暑い時期なので、熱中症対策は忘れずに!(特に水分補給)
我が家は子どもたちもいるので、毎年最後までいることは少ないです。
会場から少し離れた、中央通り商店会方面(環状七号線方面)の屋台で、焼きそばやたこ焼きなどを購入して家で食べています。
もちろん、レストランなどもお店も営業しています。
我が家は毎年、高円寺駅南口から徒歩5分ほどのカフェの、大きなフワフワのパウダースノーのようなかき氷を頂いてから参戦しています。
トイレはマップで事前に確認しよう
お囃子のリズムに乗りながら飲んだり食べたりは楽しいですが、気になるのはトイレ情報。
コンビニやお店のトイレは、ほとんど使用不可と思ってください。
阿波おどりのMAPが配布されるので、事前にトイレの場所を確認できるといいですね。
公園や公衆トイレなどいくつかあります。
友人が急にトイレに行きたくなり探していましたが、しばらく戻ってこなかったほどです。
もちろん、元いた場所に戻って見ることはできないので、覚悟してトイレに行きましょう。
事前に出来る限り行っておきましょう、としかアドバイスがありません…。
ゴミの片付けもお忘れなく
終わった後や翌日の祭りの後、学校の生徒たちやボランティアの方々が、片付け、清掃をしてくれます。
だからと言って、ポイ捨てなど迷惑になる行為は絶対にやめましょう。
ゴミは持ち帰るか、ゴミ分別収集所がありますので、そちらを利用しましょう。
まとめ
夏になると、高円寺が一つになって繰り広げられる賑やかな一体感は、ワクワクして感動します。
是非とも高円寺に足を運んで、迫力のあるおどりを体感してほしいと思います。
カウントダウンとともに3時間ノンストップの踊りがお囃子とともに始まると、夏の思い出になること間違いなしです。
♪あ やっとさ〜、やっと やっと〜♪
お読みいただきありがとうございました。